芸工展2008「丸井金猊リソース ver3.0 #10」で谷中M類栖/1f までお越しいただいた皆様、大変ありがとうございました。前エントリーでご案内したように今年は4月末から約1ヶ月、愛知県の一宮市博物館で特別展「いまあざやかに 丸井金猊展」が開催されました。展覧会図録や講演会では美術史家の山本陽子さんが金猊作品について触れられ、とりわけ屏風絵「*観音前の婚姻圖」についての作品分析が強く印象に残っています。そこで今年の芸工展は「*観音前の婚姻圖」をメインに据えた展示にしようと特別展開催中から考えていました。
「*観音前の婚姻圖」は谷中では初公開の屏風絵です。これまで展示してきた「壁畫に集ふ」よりもやや小ぶりなこの屏風は、金猊の妻・さだゑが亡くなって間もなく、当時住んでいた三鷹の住まいで遺品整理をしていたときに蔵の2階から未表装の状態で出てきました。タイトルの明記などはどこにもなく、完成しているのかどうかも定かではない。仮題「*観音前の婚姻圖」は遺族側で他の画と区別を付けやすいようにと画を見たままに名付けたものです。
法隆寺の百済観音を模したと思われる観音様を挟んだ仏前結婚ならぬ観音前結婚か?
一宮市博物館では何人かのお客様からどの女性が新婦なのか?という質問が出てきて更に戸惑わされました。私個人は画面右手の白いドレスの女性が新婦と思っていたのですが、それは少数意見で、赤いドレスの女性が新婦だという方もおられれば、金髪女性が新婦だという方もおられ、まずそもそも新婦が誰なのか判然としません。ただ、観音様だけがそれらの人物の間に立って、その存在は言うに及ばず、描かれ方からしても異彩を放っている。そこで私はその屏風の中だけではなく、屏風のまわりにも金猊の描いた人物たちを並べてみたら面白いのではないかと思い、今回の芸工展では人物画限定の展示を行うことにしました。
そこでまず思い描いたのは、特別展「いまあざやかに 丸井金猊展」では作品の傷みが激しいという理由で展示を見送られた江南の叔父のところにある「*聖徳太子二童子像」2点を展示しようということでした。法隆寺繋がりという捉え方もできますが、これによって東京方面から愛知県まではるばる足を運んでくださった方にも未見の作品があるという楽しみをお持ちいただけたのではないかと思います。
そして、もう一つの目玉として、所在不明となっている「ハープとピアノ」という作品の下絵を展示しました。この「ハープとピアノ」の下絵は2点あり、完成作の様子はアルバムに残されていたセピア色の写真1枚によってしか知り得ないのですが、今回展示した下絵はその完成作とは異なるものの方です。見較べていただければ一目瞭然ですが、ピアノを弾いている人物が今回展示した下絵は男性、完成作では女性で、完成作には犬も描かれています。もう一つの下絵はその完成作と同じもので、一宮市博物館でも展示の計画はあったのですが、スペースの都合から見送られました。尚、うちで完成作でない方の下絵を選んだのは、そちらの方が下絵の上部がしっかりしていて、画鋲で留めやすかったこと。もう一つは下絵の線が濃く描かれていて、他の実作と比較されても見劣りしないで済みそうだと思えたからです。
一宮市博物館の特別展以前も下絵の展示は何度か行ってきましたが、谷中では初めての試みで、ギャラリー仕様とはいえ、居室でもある空間で合うかどうか、実際に展示してみるまでは若干心配でもありました。しかし、その心配は杞憂に終わったと言えそうで、今後も下絵をポジティヴに「新作」と捉え直して随時公開していきたいと考えています。
他、今年の展示作品は去年も展示した軸の「浴女」と毎年展示している版画の「さだゑ圖」、そして谷中では初出となる「婦女圖」、菊池契月の模写画「稚児圖條暢」を展示して人物画としてまとめました。しかし、人物画とは言っているものの、それらの人物たちはどれもリアルな肉感を讃える描写と言うにはほど遠く、金猊の妻・さだゑの言葉を借りれば「霞を食べて生きている」ような人物像ばかり。基本的には金猊が若い時分に何度となく模写を繰り返した仏像や歴史画の人相に近いものがあります。
そんな中、生身の人間としては描かれていないはずの観音様。他の人物の誰よりも荒々しく描写されているその御顔を拝んでいると、何だかとても人間味を帯びているように見えてくるという(私個人には金猊の母親の顔に似ているように見えてくる)、そんな不思議感覚を谷中M類栖/1f の空間でも楽しんでいただけたらと思っておりました。
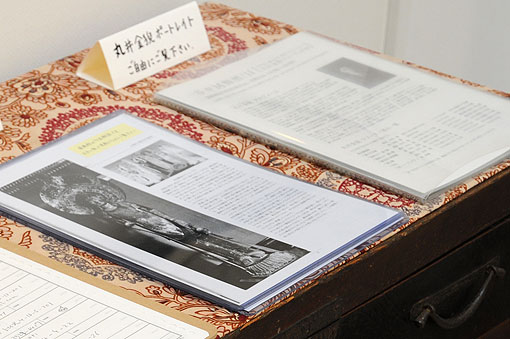
しかし、こういう展示でなかなかコンセプチュアルな主旨を伝えるというのは容易ではなく、美術史家の山本陽子さんが図録で書かれた「*観音前の婚姻圖」の作品分析も一部抜粋して会場で読めるようにしておいたのですが、会場内の「他のお客さんという人物」が存外にたくさんいらっしゃる中で集中してテクストをお読みいただくというのは難しく、そういう話はなるべく口答で話しかけるようにしていった方がよさそうだというのが今後の課題として見えてきました。
また、個人住居にドアホンを鳴らして入場することの敷居の高さという去年までの課題については、去年知人の中では唯一お越しいただいた flickr 仲間の otarakoさんのアドバイスに従って、今年は最初から玄関ドアを全開にしたので、以前よりも通りがかりのお客さんの数がだいぶ増えたように実感しています(今年も招き猫ならぬマネキオタラコスモスの効果絶大でした♪)。
また、一宮市博物館の特別展で使われた年表や写真などの展示パネルを譲り受けたので、お陰様で今回の展示から金猊本人の輪郭は俄然捉えやすくなったように思います。ただ、年表は横幅が180cmあり、それを展示空間に持ってくると2作品分くらい取ってしまうので、玄関前室に設置する以外なく、重たい年表を下にして、「菊花讃頌」パネルを華燈窓のところに置きました。この組み合わせは毎年定番ということになりそうです。
来年は金猊生誕100年ということで、10月19日という金猊の誕生日もちょうど芸工展期間内となるので、今年よりは会期に余裕を持たせての展示を行いたいと思います。
こんな感じで谷中M類栖/1f のドアが全開のときは、是非お気軽にお立ち寄りください。
















